今回は、デザイン制作を外注(発注)している方向けの記事になります。
私自身、これまで発注者として複数のデザイナーに依頼してきましたが、中には「プロ価格」を請求しながらも、成果物が想定以下だったり、修正対応で追加費用を求めてくる方もいました。
そうしたやり取りの中で、依頼者側が不利にならないために感じたこと・学んだことをご紹介します。
最初からの値上げ交渉、そのとき依頼者は…
実際にあったやり取りの一例です。
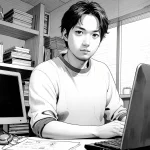 わたし
わたしクライアントからデザイン作成の依頼がありまして。この依頼内容なら、作業時間は10時間程度なので、20,000円でお願いできますか?時給¥2,000くらいを想定しています



いえ、このボリューム感なら25,000円でお願いします
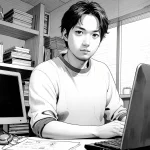
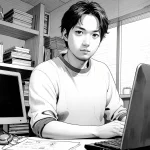
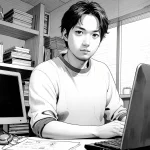
(急なお願いというのもあるから)しょうがないですね、それでお願いします



ありがとうございます!精一杯対応します!
正式依頼の前段階で、当初想定より高い金額を提示されることがあります。
相場がわからない、早く着手してほしい…そんな理由でそのまま受け入れてしまう依頼者も多いのではないでしょうか。
しかし、明確な作業範囲や追加要素の根拠がないままの値上げは、依頼者にとって非常に不利です。
初稿提出で…
このデザイナーの方の初稿をみて、クライアントと私とさらにもう一人の計3人で確認したところ。
メインビジュアルのイメージが希望と合っていない。これが満場一致でした。そこで。
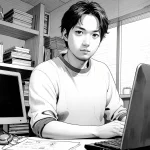
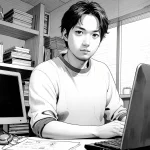
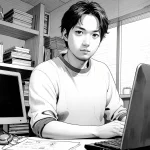
メインビジュアルの作り直しをお願いできますか?



修正は1回までで、これが最後になりますが大丈夫ですか?それ以上の修正は追加費用を相談したいです。
こういう返信がありました。これ、依頼者側がかなり不利なのがわかりますか?
そもそも依頼者側の3人が見て、3人ともが希望のデザインと違うと思うデザインなのに、修正回数の縛りをしてくる。そして、追加費用の相談….
こんなのデザイナー側が適当なデザイン作ってしまえば、必ず修正来て追加費用を請求できるようにもなるじゃないか!
最終提出で…
結局、私自身が修正作業は請け負うことにして、デザイナーの作業はここで停止しました。
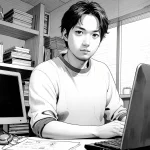
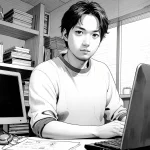
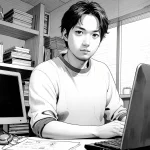
今回はこれで終了で大丈夫です。ただ元々の希望金額から値上げ交渉されておいて、この対応だと依頼者側は結構辛いです…



これが私のクオリティなので、ご不満があれば次回からは依頼していただかなくて大丈夫です…
なんてこった…。もちろん、二度と依頼はしないですよね。
なぜこんなことが起きるのか?
こうしたケースは、フリーランス歴が浅いデザイナーや駆け出しコーダーに多く見られます。
背景には次のような心理や習慣があります。
- 安定案件がない → 一回でできるだけ取ろう
定期的な案件がないため、1件でできるだけ多く稼ぎたい心理が働く。 - 「単価は下げるな」という教え → 実力に合わなくても高単価
スクールや先輩から「単価を下げると価値が下がる」と言われ、経験不足でも市場の上限価格を提示。 - 労力=価値という思い込み → 品質より“頑張った時間”基準
「長時間かけた=価値が高い」と勘違いし、クオリティや再現性の低さを認識できない。 - 修正は有料が当たり前 → 防御的な姿勢
修正を「自分のミスを直す場」ではなく「追加作業」と捉え、すぐに追加請求につなげる。
依頼者に降りかかる“四重苦”
こうした相手に依頼すると、次のような負担が生じます。
- 高単価 × 低提案力
細かく指示しないと進まない。結果、依頼者が構成やデザイン案まで考えることに。 - 仕様内なのに修正有料化
色味や文字修正など軽微な変更すら追加費用になる。 - ディレクション負担増
提案が出ず、依頼者が実質ディレクターを兼ねる。 - 依頼前からの単価引き上げ
発注直前で金額を吊り上げられ、比較検討できないまま契約。
発注前に確認すべき4つの質
契約前に、必ず以下の質問をしましょう。
- 最新の実績3件と担当範囲
→ どこまで自分が関わったかを明確に説明できるか - 参考デザインの再現事例
→ 指定したテイストを過去に再現できているか - 修正範囲と回数
→ 仕様内と仕様変更の線引きを合意できるか - 金額変更ルール
→ 追加費用発生の条件と計算方法を事前に明文化
契約で揉めないために
- 修正回数と範囲を明文化(例:仕様内修正は3回まで無料)
- 中間レビューを設定(初稿・60%・90%)
- 検収条件を明記(主要ブラウザ・端末での動作確認など)
- 仕様変更・追加費用の定義を具体化
- 金額変更は双方の事前合意を必須とする
進行中のコツ
- 修正依頼は「目的+具体的指示+期限」で伝える
- 初稿段階で方向性を固め、細部は後半に
- 条件変更の提案は即確認&書面化
- やり取りは必ず記録として残す
まとめ
デザインの価格は**“肩書き”ではなく“成果と姿勢”**で決まります。
依頼者は「発注前の見極め」「契約の線引き」「中間レビュー」「金額変更ルールの合意」で主導権を握ることが大切です。
そうすれば、高単価低品質+修正有料化+依頼前の値上げという地雷案件を避け、納得のいく成果を得られるでしょう。
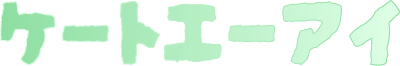
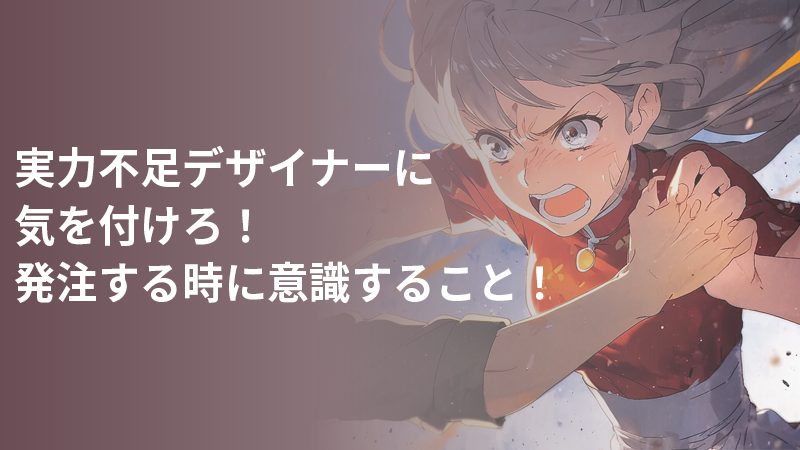
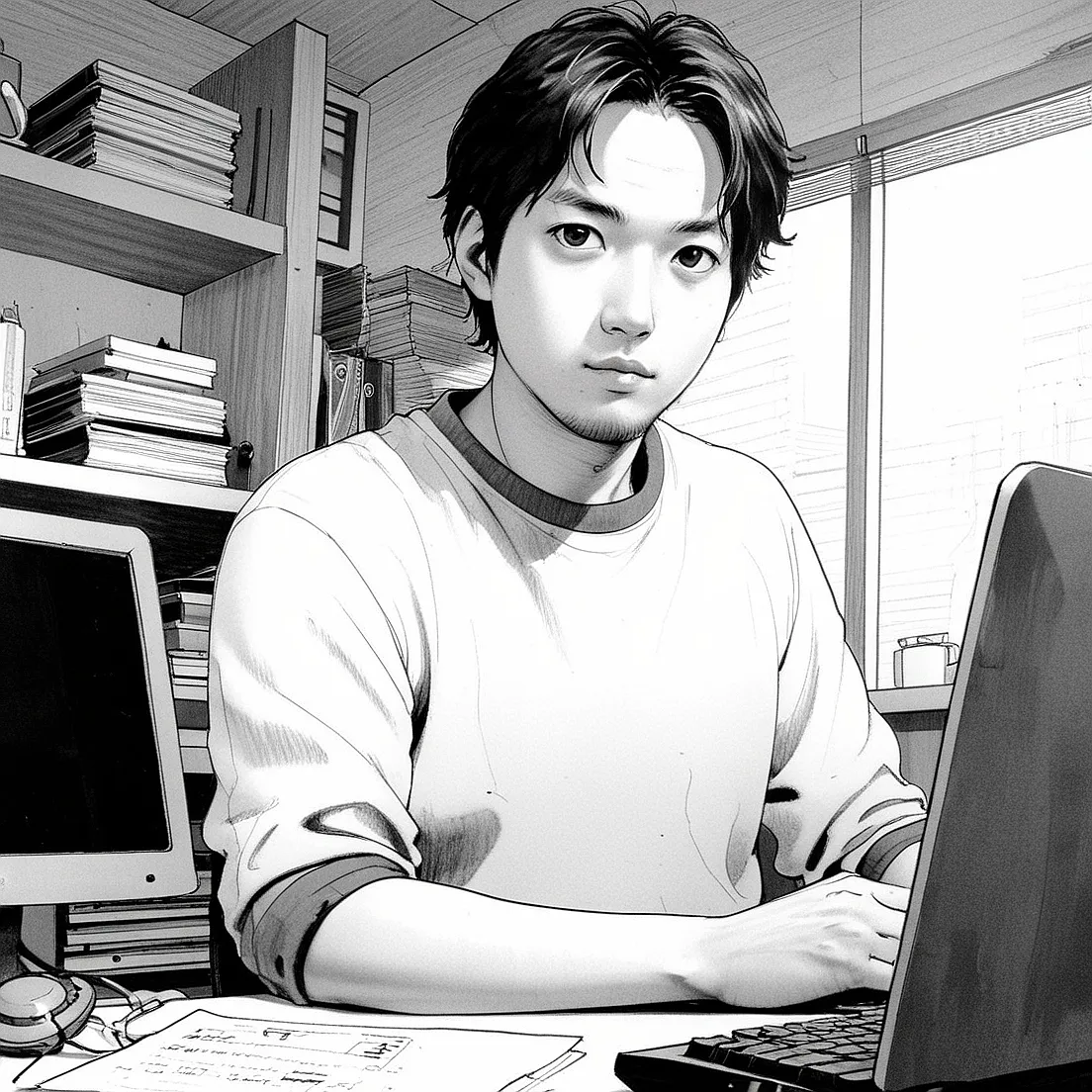


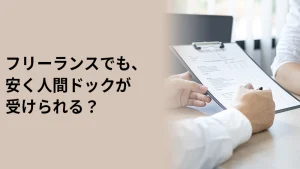
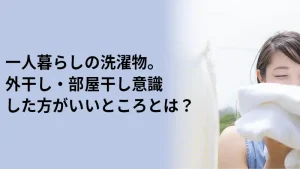
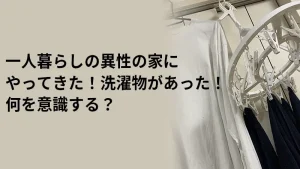

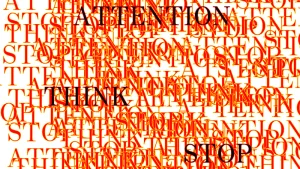

当記事に対してのコメントをご記載くださいませ!